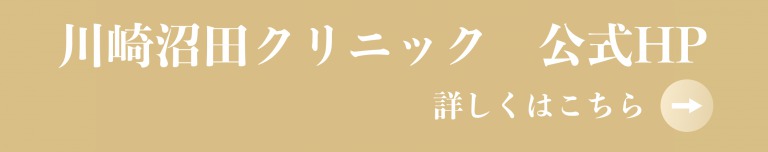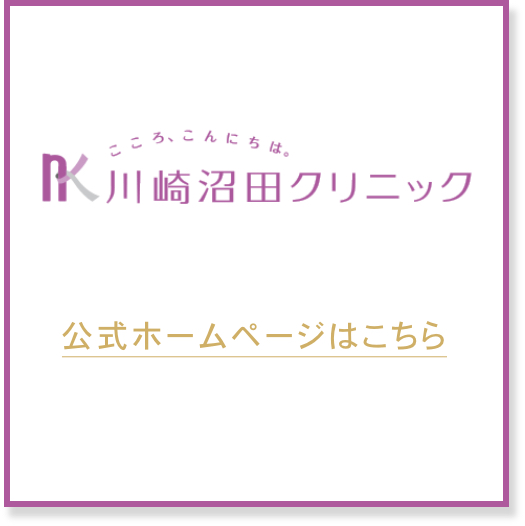30Jun

今回は「へこむ」という意味で、あえて「しょげる」という表現を使います。
「しょげる」ことが美徳とされる場面
日常生活や職場、学校、そしてSNSの場面でも、「申し訳なさそうな態度」を求められることがあります。
ちょっとしたミスや誤解でも、ただ説明するだけでは不十分で、「しょぼん」とした態度や、下を向いた表情まで求められる。悪気がなかったとしても、「しょげていない=反省していない」と見なされる空気があります。
こうした背景には、日本文化に根づく「潔さの美化」や「儀式的な謝罪」の風土が深く関わっています。
「潔さ」に執着する文化的背景
●時代劇の象徴:「潔く腹を切れ」という決めゼリフ
時代劇『暴れん坊将軍』では、悪事を暴かれた登場人物に対して、「潔く腹を切れ!」という決まり文句が放たれます。
これは単なる演出ではなく、責任の取り方としての“潔さ”が最も美しいとされる日本独特の美意識を象徴しています。
●恥の文化と世間体の力
ルース・ベネディクトの『菊と刀』で指摘されたように、日本社会は「罪の文化」ではなく「恥の文化」に分類されます。
つまり、何が悪かったかよりも、「他人からどう見られるか」「世間体」が行動の基準となるのです。
そのため、「謝ったかどうか」よりも、「どれほどしょげていたか」「申し訳なさそうだったか」といった態度の部分に焦点が当たりがちになります。
●“けじめ文化”と儀式としての謝罪
さらに、日本には“けじめ文化”と呼ばれる特有の考え方があります。これは問題の本質的な解決よりも、「どんな態度で責任を取ったか」に重きが置かれる傾向のことです。
SNSでの長文謝罪、会見での深々としたお辞儀、職場での繰り返しの謝罪——これらは単なる誠意ではなく、周囲への“儀式的な納得の提供”であり、「責任を取った」ことの演出なのです。

「投影性同一視」で他人にしょげさせる心理
ここで浮かび上がってくるのが、謝らせる側・しょげさせる側の心理構造です。これは精神分析の用語で「投影性同一視(projective identification)」と呼ばれる心の働きに関係しています。
つまり、自分の中にある罪悪感・後悔・不安などを、自分のものとして意識せず、他人に“持たせる”ことによって、自分がそれを感じずに済むようにする働きです。
たとえば「お前がちゃんと反省しろ」「潔く謝れ」「しょげる姿勢を見せろ」と繰り返し圧をかけるのは、自分の内面にある処理しきれない感情を、他人に演じさせ、代わりに背負わせようとする無意識の操作です。
そして相手が実際にしょげたり、泣いたり、落ち込んだりする姿を見ると、自分の中の“しんどさ”がなぜか晴れていく——それが「投影性同一視」の効果なのです。
しょげる自由と、しょげない自由を取り戻す
「潔く腹を切れ」という言葉に象徴されるように、日本には美しく責任を取ることを求める文化的要請があります。しかしそれが他人への「しょげろ」という圧力に変わったとき、そこには歪みが生じます。
しょげない人に「反省していない」と決めつけたり、形だけの謝罪を繰り返させたりすることは、本当の意味での対話や理解を遠ざけてしまう。
私たちは、しょげることで安心する文化に生きています。けれども、それが過剰に他人にまで求められると、誰もが「責任役」を押しつけ合う息苦しい社会になります。
「そこまでしょげる必要がありますか?」という問いは、相手に対する優しさであると同時に、文化に対する冷静な距離の取り方でもあるのです。
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、投影性同一視の他、さまざまな精神的お悩みをお持ちの方のカウンセリングを行っております。下記HPよりお気軽にお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
▼「投影性同一視」に関連する記事は他にもございます。ぜひあわせてご覧ください。
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。