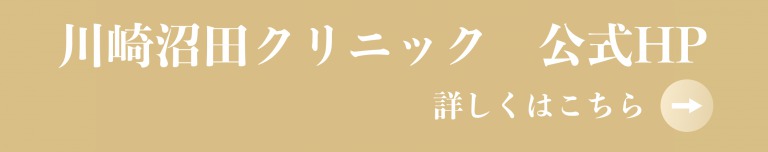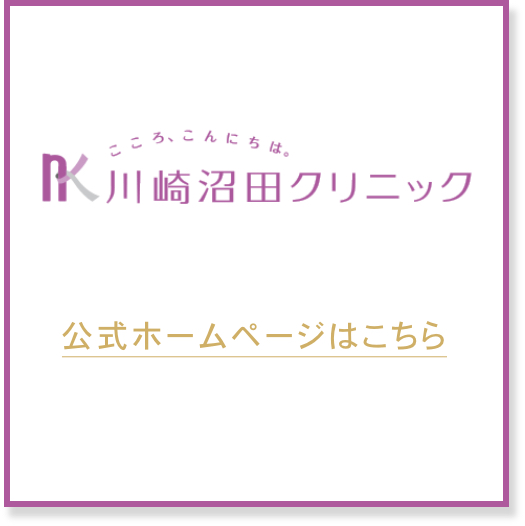20Apr
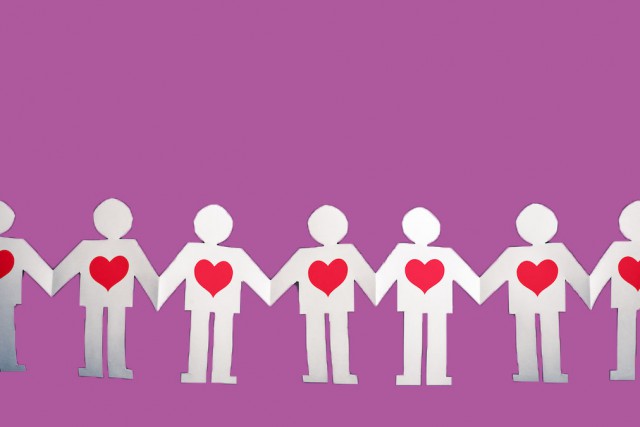
今回は身近で遭遇した出来事を心理バイアスにあわせて述べていきます。今回取り上げる事例は、男性アイドルグループのコンサートが終わったあとの最寄駅で見かけた事象です。推し活のために行列に並ぶ人たちの心理に迫ります。
見えない心理的“共感の地図”が導く推し活の行列
仙台駅の新幹線口には、ずんだシェイクで知られる「A」と、そのすぐ近くにある「B」があります。どちらもずんだを使ったスイーツを提供しているにもかかわらず、コンサートが終わった直後の若い女性たちは、閉店しているのにも関わらずAの前で名残惜しそうに立ち尽くし、すぐそばの開いているBにはなかなか足を向けません。
これは、単なる味の好みやブランド認知だけでは語れない、象徴的な現象だと考えられます。その背景には、押し活するひと個人の中にある「心理的な地図」と、他者との関係性を維持しようとする「集団帰属」の欲求が複雑に絡んでいます。
多くのファンにとって、ライブという高揚体験の後には「推しと同じことをして推し活したい」という心理が自然と働きます。Aは、過去にかつて同じ事務所の著名なメンバーが紹介したことで、ファンにとっては「推しが訪れた場所=聖地」として記憶されていたのです。
推し活の心理「バントワゴン効果」
そのため、たとえ閉店していても「そこに向かうこと自体」が、ファンとしての忠誠や連帯感を示す一種の儀式になっているのです。また、周囲にいる他のファンたちも同じ目的で推し活行動しているため、集団としての方向性が自然と形成されています。
ここで注目すべきなのが、いわゆる「バンドワゴン効果」という社会心理です。他の人が同じ行動をとっていると「それが正しい」と無意識のうちに信じてしまう傾向があります。さらに、ジャニーズファンのようなコミュニティでは“仲間と同じ体験をする”ことが非常に重視されていて、一人だけ別の選択をすることに、まるで“集団から外れる”ような不安が伴います。このように、推し活する人の心理的な地図の中では「Bへ行く」という選択は“正解”ではなく、“物語の外側”へと踏み出すように感じられるのです。

推し活体験の文脈と“代替不可能性”の心理「共体験消費」「擬似接触効果」
ここで浮かび上がってくるのが、「同じような商品なのに、なぜ代替されないのか?」という疑問です。AのシェイクとBのそれは、価格も味もほとんど変わりません。しかし、ファンにとっては「場所」や「名前」こそが意味の中心であり、体験価値を支える土台になっています。
この現象は、現代のファン行動に特有の「共体験消費」や「擬似接触効果」によって説明できます。推しが紹介した商品を自分も味わう推し活は、まるで本人と接触しているかのような感覚をもたらします。そして、その体験を推し活仲間と分かち合い、SNSに投稿することで、さらにその感覚が強化されます。重要なのは「何を食べたか」ではなく、「どこで、誰と、どんな気持ちで食べたか」という“文脈”なのです。
また、推しとの同一化を図るためには「推しと同じ選択をする」ことが欠かせません。だからこそ、「本日は閉店しています」という案内が出ていたとしても、他の選択肢に移ることができないのです。それは「それを選んでしまうと、自分は推しと同じ体験をしたとは言えない」と感じてしまうからです。こうした判断は、理性的な思考というよりも、物語への没入と心理的な忠誠心に基づいていると考えられます。
最終的に、推し活をする彼女たちが列を作るのは、ずんだシェイクを買うためではなく、“推しと同じ時間”をもう一度味わうためであり、仲間との一体感を確かめるためなのです。それはすでに、消費というよりも儀式であり、参加型の物語だと言えるでしょう。
「限定」という思いからさらに強化される推し活心理
これらに加えて、「 (仙台に来て) せっかくだから」という限定心理が、さらに購買行動を強化します。「わざわざ仙台まで来た」という行動の意味がさらに強化されることにもつながります。自分へのご褒美という感覚です。従ってAが既に売り切れでこれ以上並んでいても買えない段階で、かつBがまだ開店中であっても、Bには並ばないと現象が生じています。
つまりこのような購買によって欲しいのは「モノ」そのものありません。モノを「体験」に置換しているということなのでしょう。私たちは知らず知らずのうちに、「自分の選択が良かった」と確認したい衝動に駆られるのでしょう。
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、さまざまな精神的お悩みをお持ちの方の診察を行っております。下記HPよりお気軽にお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。