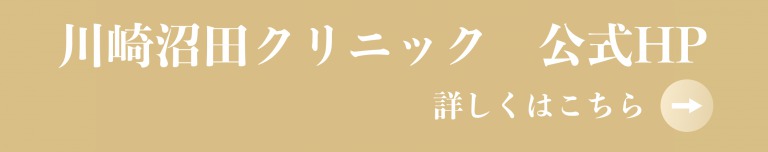CATEGORY人間関係・いじめ・ハラスメント

「そこまでしょげる必要がありますか?」: 潔さを強いる文化と“謝らせたい心”の正体
今回は「へこむ」という意味で、あえて「しょげる」という表現を使います。 「しょげる」ことが美徳とされる場面 日常生活や職場、学校、そしてSNSの場面でも、「申し訳なさそうな態度」を求められることがあります。ちょっとしたミスや誤…

投影性同一視と煽り運転:「お前は何やってんだ」の心理
クラクションに映る、自分の内なる不安…投影性同一視のメカニズム 最近、煽り運転が社会問題としてたびたび取り上げられています。中には、前の車が少しブレーキを踏んだだけで、クラクションを鳴らし、怒鳴りながら運転席に詰め寄る――そんなニュ…

対人関係には能力に応じた「学年」がある(後) : 少しずつ学ぶ提案が拒否される理由
今回は”対人関係の(能力に応じた)学年”を意識することに対する内容をまとめた後編です。我々援助者側の戒めも入っています。前半の記事をまだご覧になっていない方は、ぜひそちらからおさらいしてみてください。 ▼前半の記事はこちら …

対人関係には能力に応じた「学年」がある (前) : 九九も割り算もすっ飛ばして、因数分解レベルを求める心理
今回は対人関係援助の流れについて述べます。DVや虐待、パワハラといった強要、騒ぐといった形のぎくしゃくなどの対人関係ついて、”対人関係には能力に応じた「学年」がある”ということをテーマに迫っていきます。内容は援助職としての自らの戒めも含み…

言い合いがループするとき、言いたい相手は“そこにいない人”なのかもしれません
言い合いが“ループ”する感覚 会話の中で、なぜか話が前に進まず、同じやりとりが繰り返されることはないでしょうか?たとえば、サービス窓口でのクレームや、病院や役所での怒鳴り声。相手が説明しても、なぜかまた最初に戻ってしまう。終わる気配…
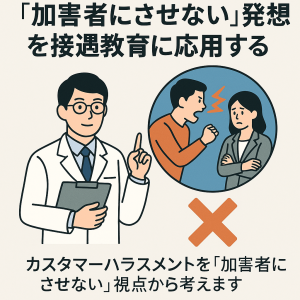
カスタマーハラスメントの対応【接遇教育】
精神科の現場では、いわゆるカスタマーハラスメント(クレーマー)に対しては、患者さんを「加害者にさせない」という観点から、対応の在り方を共有しています。わかりやすく「カスタマーハラスメントから組織を守るにはどうしたらよいか」という方向性を優…
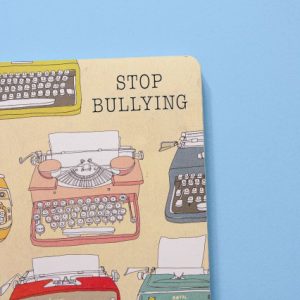
「気難しさ」や「めんどくささ」の奥にあるもの
はじめに 「めんどくさい人」「気難しい人」と言われる様子が。時に自分自身がそう感じられることもあるかもしれません。でも、私たちはその表面的な態度や反応だけを見て判断してしまいがちです。このブログでは、私たちがなぜ気難しくなってしまう…

「ほっとけへんのや」は美学ではない
この項目は関西弁を例として述べていきます。関西の方から見れば「そういう意味じゃない」と捉える想定も前提としていますが、あくまで言葉から来るその人間関係と距離感をわかりやすくするために用いています。今回は読み物としてご覧ください。 「…

パワハラ問題への本質的アプローチ-家族背景を見つめる(後)
今回の項の前半はパワハラから始まり、暴走行為など衰退した衝動行為の流れを述べました。時代が事象に適正に距離を取る方向に動いていくことを期待し、現在の問題であるSNS攻撃について発展させます。 ▼前半の記事はこちら https…

パワハラ問題への本質的アプローチ-家族背景を見つめる(前)
今回は最初はパワハラ(パワーハラスメント)を題材として、人間関係の関連性を照らし合わせて述べます。 1. パワハラは単なる個人間トラブルではない 俗に言うパワハラが発生した場合、私たちは表面的な二者関係の問題として処理すること…