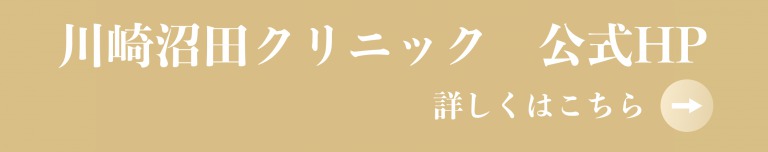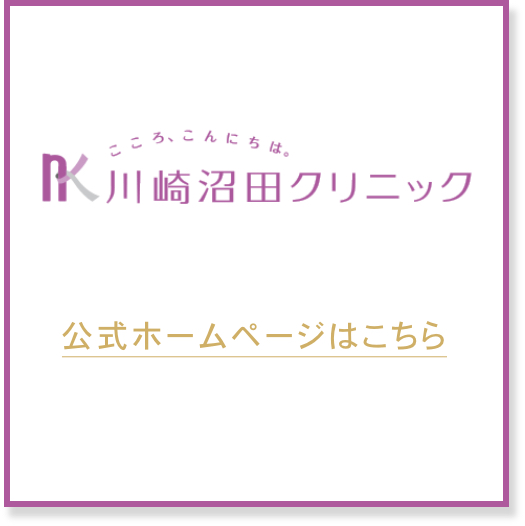25Aug

今回は当院の対人関係問題の治療方針である「加害者にさせない」方向性というポイントから、加害者心理が意外なところから湧き出でてしまっているところを説明します。
共依存にも通じるところがあります。
無償の援助が抱える逆説
家族関係に悩んできた人の中には、「本当は頼りたい相手にほど噛みついてしまう」という行動をとる方が少なくありません。これは一見すると矛盾した振る舞いですが、背後には「無償の援助」への複雑な感情があります。
親子関係の中で「面倒見」は愛情の象徴であると同時に、「裏切ってはいけない」「切ってはいけない」という縛りを生むことがあります。受け取った側にとっては、「一生返さなければならない」という重荷として感じられ、その“いつまでも”という無限の義務感に耐えられなくなったとき、逆に「自分は面倒を見てもらった覚えはない」と合理化して反発するのです。
つまり、無償で与えられる援助は「感謝」ではなく「負債」として認識される危険があり、そこから攻撃的な反応が生じます。
援助者が加害者と見なされる瞬間
このような心理構造のもとでは、援助を受けた側が援助者を「加害者」とみなしてしまうことがあります。
– 無償で支援を受けた → 義務を背負わされたように感じる
– 義務感から逃れるため → 「自分は悪くない」という合理化が働く
– その結果 → 援助者への反発や攻撃が生じる
依存症や対人関係のもつれにおいても、このパターンは繰り返されます。例えば医療や福祉の現場で「良かれと思って手を差し伸べたのに、逆に攻撃される」という経験は珍しくありません。援助する側にとっては戸惑いや無力感を覚える瞬間ですが、相手にとっては「家族関係での再演」になっており、無意識に攻撃せざるを得ない立場に追い込まれているのです。
援助者が「加害者」と映るのは、支援そのものが悪いのではなく、援助を受ける側の内面にある「面倒見の縛り」が再び作動してしまうからだと理解することが大切です。

社会における「面倒見」の再演
この構造は家庭の枠を超えて、公共機関やボランティア活動、さらには日常の人間関係にまで現れます。例えば「ただでやってもらう」という経験が、「一生縛られる」という誤解を呼び起こすのです。
例えば敵意帰属バイアスの心理構造の一環である、煽り運転に見られる「俺は悪くない」という反応も、背後には「お前は面倒を見られるべき存在だ」という無意識のメッセージが伏線のように潜んでいます。
こうした反応は、援助を受けることが「弱さの証」とみなされやすい文化的背景とも重なり、さらに攻撃的な表現を強めてしまいます。支援の現場では、このような「再演の罠」に巻き込まれることが少なくなく、援助する側が「なぜ恨まれるのか」と感じてしまう原因になります。
援助と境界線を守るために
無償の援助は温かさを届ける一方で、境界線を曖昧にしやすい危険性をもっています。家族関係の「面倒見」と重なることで、支援者が知らぬ間に「裏切ってはいけない存在」として縛られてしまうからです。
だからこそ援助の場面では、「無償だからこそ限度がある」「援助は永遠の義務ではなく、一時的な関わりである」という合意が重要です。援助を提供する人が悪いわけでも、援助を受ける人が未熟なわけでもありません。ただ、両者の間に境界線が設けられないと、支援が負担や攻撃に転化してしまうのです。
支援する側にとって大切なのは、「相手が感謝してくれるかどうか」よりも、「境界線をどう守るか」という視点です。支援はあくまで一時的な関わりであり、双方が自由であることを確認する。その工夫こそが、援助を健全に続けるための最も確実な方法だと言えるでしょう。
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、さまざまな精神的なお悩みをお持ち方の診察を行っております。下記HPよりお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。