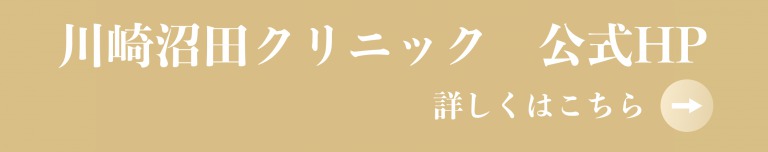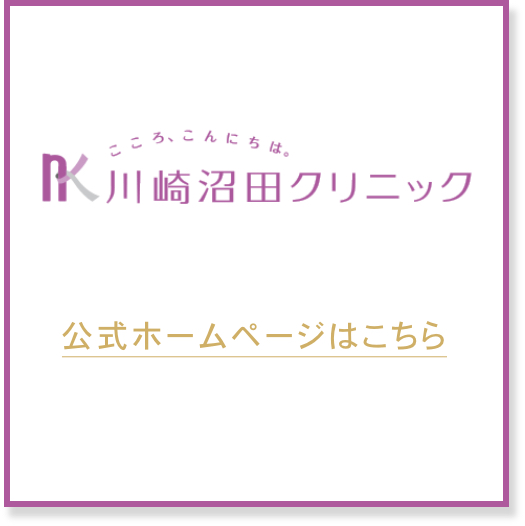2Feb

今回と次回は、近頃AC JAPANの広告からです。気付かないうちにやっていること、あるいは世相への喚起などについて、既に先回りして制作しているCMがあることに多少驚きを感じています。
決めつけ刑事(デカ)-利用可能性ヒューリスティクス
一つ目は、「決めつけ刑事 (デカ) 」と銘打った喚起広告です。冤罪になるシーンを取り上げて、「ネットの中でみんなが○○と言っている」という内容から逮捕されそうになる場面を取り上げています。
この中で私が注目しているのは、決めつけていることそのものではなく、あくまで決めつけるまでの過程です。
実際に描かれる取り調べ場面では犯人にする決め手に欠けるところで、決め手がなくそろそろ釈放かと刑事たちが悩むところで、別の刑事がネットの情報をもとに容疑者に迫るシーンとなっています。
ここで大切なポイントは、不確実なネット情報をもとに安直に決めつけないことではありません。
このCMの場面では、刑事側が望む方向に解決しないつまり逮捕できないという空気感になった瞬間、「責任を被らされる」「これまでやってきた行動に成果が伴わない」という思いが広がります。その思いが現実になることを打ち消そうとして、強引にこれまでやってきたことが報われる方向に埋めようと進める流れです。
これを「合理化」と言います。
私たちは実は日常的に合理化に近いことを頻繁に行っています。しかし一人でやっている場合は実は「昇華」と言われる場面もあり、精神衛生的には良好な方向に働くこともあります。そこには強引さはありません。
しかし複数の人間が互いに合理化場面に関与した時には、全体として大きな疑義を起こすことになります。なぜかというとこの時の複数の人間達は、それぞれ立場が異なってくるからです。最初は逮捕に向けて一致団結していますが、雲行きが変われば各々の責任がちらついてきます。
このように、こと「誰の責任か」となったときには、それまでの平等性を保とうとする動きが働き、その結果「最もその立場に近く見える人」(これは立場が弱い人あるいは強い人という意味ではありません。波風が最も立たないように仕向けられる相手という意味です) に責任を擦り付けて、簡単に裁いてしまおうと試みる衝動に、関係者全体が駆られることがあります。

SNS企業の思惑 -「事実」以上に「感情」を拡散して欲しい
この広告場面では「容疑者」ですが、実際の社会では「明確に損害を被る人」を相手に、ネットやSNSでつるし上げることに参加したくなる衝動に「駆られる」ことがあります。
いわゆる「私的警察」「ネット警察」といわれ、相手が俗に有名であれば大きくなります。これは相手を動かした時に、ギャラリーつまり周りの賛同を想定するからです。相手にしているのは、対象の変化ではなくギャラリーの反応そのものとなっています。
この正義感は、実は常にギャラリーを意識しています。従って早い応答に駆られ、従って現在の情報と当時者の経験で「決めつけたい」衝動に駆られます。
もう一つ、「決めつけたい」衝動に駆られる理由があります。これは情報がない段階で実は私の望む方向と異なる事実であったら、トラウマ当事者の経験は当事者の経験に過ぎないと、自ら沈む方向にオーバーラップしてしまう危機感に駆られるです。
「私だけ特別な状態が降りかかってきた」と認識して孤独を感じなければならなくなる怖さから離れるためには、私と同じで「きっと○○に決まっている」とした方が、向き合いやすくなります。
「私だけじゃない」と思いたい衝動を推進するためには、「絶対に○○に決まっている」という方向にもっていきたくなってしまいます。
これをSNSの企業は狙っていると言えるでしょう。従ってこの思い込みをSNSに素早く反応してくれるように、リプライ機能やいいね機能を作っています。
流行させて競争に勝たなければならない企業のミッションですから、裏には公には言えない狙いがあります。SNSの会社は「事実の拡散」という建前で、本音は「感情の拡散」を企業反映の土台として必要としているように見えます。
年々短くなる仕組み作りが配信動画サイトが流行するのは、作成への手間への配慮もさながら、実は「瞬間的に浮かんだ感情」こそが最も鋭くてわかりやすく映り、従って拡散衝動につながるからなのでしょう。
ちなみにこのような流れを行動心理学用語で「利用可能性ヒューリスティクス」といいます。あくまで発信者が理解しやすい範囲で、物事を結論付けようとする心理バイアスです。
人間関係再構築は「そうとは限らない」の会得
「またあの時と同じ」あるいは「あなたも私と同じに決まっている」と考えることで、すぐに腑に落ちる状態に持っていこうとする気持ちに駆られるのが、トラウマの影響とも言えます。
従って人間関係でのトラウマ影響の再構築の方向は、「○○に決まっている」から「○○とは限らない」というスタンスを身体で取り戻していくことになります。確かにトラウマ体験が長期間に及ぶ場合や、幼少期からの影響がある場合は、取り戻しに加えて、新たに培う部分もあるでしょう。
しかしこれからの新しい体験と治療を併せていく中で、日々やってくる一つ一つの情報について、「そういうこともあるかもな」と距離を置きながら咀嚼できるようになることを目指していきます。
▼後半の記事はこちら
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、人間関係でお悩みの方の診察も行っております。下記HPよりお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。