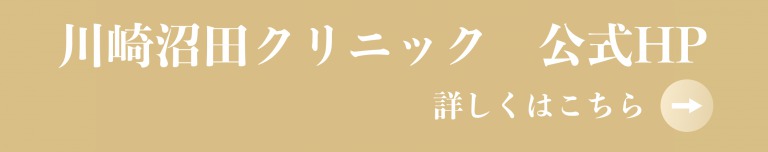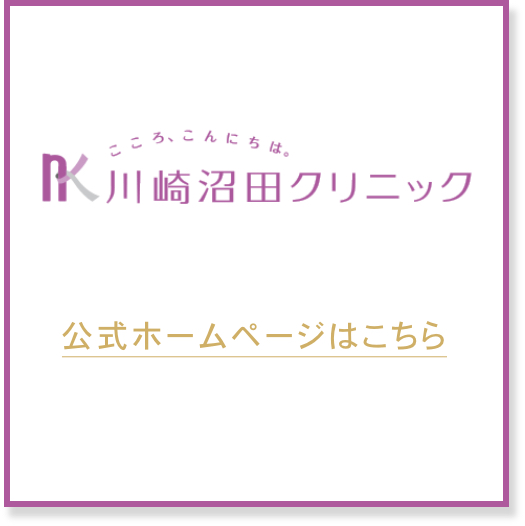20Apr

消えないトラウマがもたらす共感と巻き込みのあいだで
「どこまでが自分で、どこからが相手なのかがわからない」──こう感じる人は少なくありません。特に過去にトラウマ体験を抱えた人は現在でもトラウマ経験が影響し続けている場合が多く、人との距離感が極端に近くなったり、逆に誰にも触れさせないようになったり、どちらかに偏る傾向があります。トラウマ経験により心の傷を負ったとき、人は境界線を引くことに恐れを抱きます。「嫌われるのでは」「見捨てられるのでは」といった不安が、相手との距離の調整を難しくしてしまうのです。
そうして曖昧になった境界線の中で、相手に自分の感情が乗り移ったり、逆に相手の怒りや悲しみを自分のもののように感じてしまったりする。これは「共感性」や「優しさ」とは少し違う、“巻き込まれ”の状態とも言えるでしょう。
消えないトラウマを抱えた人は、「分かってほしい」という気持ちが強い一方で、「分かりすぎること」にも無防備になりやすいという二重の構造を持っています。だから、時に些細なひと言に傷ついたり、相手の感情の波に呑まれやすくなったりします。
これらはすべて、過去の記憶と現在の出来事が、無意識のうちに重なり合ってしまうことから起こります。「あの時」と「今」が繋がって感じられるために、防衛的な反応や過敏な受け止めが起こりやすくなるのです。こうした「心の地続き感」が、対人関係の中での“見境のなさ”や“感情の過剰反応”として表れることがあります。
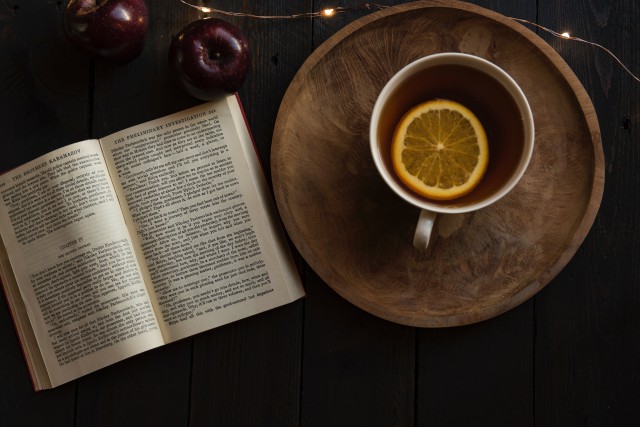
消えないトラウマと付き合いながらも、自分を保ちつつ関わるということ
境界線とは、「線を引いて相手を拒絶すること」ではなく、「自分と他者をきちんと分けたうえで、適切な距離をとること」です。その距離感があるからこそ、健康な共感や、必要に応じた支え合いが可能になります。消えないトラウマの影響でその線が曖昧になっているときは、「自分はどんなときに相手に巻き込まれやすいか」「なぜその人の言葉があんなに刺さったのか」など、自分の内側を丁寧に振り返ることが大切です。
日本社会では「察する文化」や「空気を読む力」が求められる場面が多いため、境界線を保つこと自体が難しい側面もあります。ですが、本来の意味での“共感”とは、相手の感情を一体化して背負うことではなく、「その人の感じ方をその人のものとして理解すること」です。他者の痛みをそのまま自分の中に引き取らなくてもいい。むしろ、距離を取って観察し、自分を保ったまま関わることこそが、持続可能な人間関係の鍵になります。
心の境界線があいまいなままだと、他者とつながろうとすればするほど、自分のエネルギーが削られていきます。だからこそ、「これは自分の感情なのか、それとも相手のものなのか」と問い直す視点を持つこと。それが、消えないトラウマに縛られない揺らがない自分軸を育てる第一歩になるのです。
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、トラウマをはじめとする、さまざまな精神的お悩みをお持ちの方の診察を行っております。下記HPよりお気軽にお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。