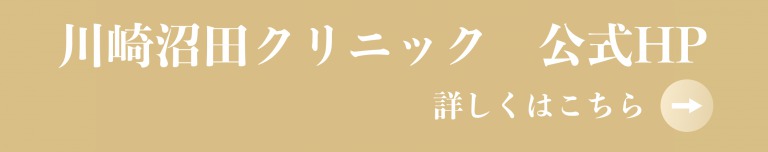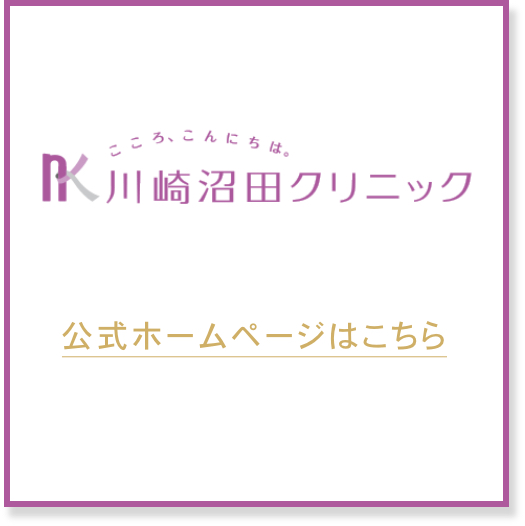20May

この項目は関西弁を例として述べていきます。関西の方から見れば「そういう意味じゃない」と捉える想定も前提としていますが、あくまで言葉から来るその人間関係と距離感をわかりやすくするために用いています。今回は読み物としてご覧ください。
「情の人」のつもりが、境界を越えていく
「ほっとけへんのや」。関西弁でよく聞かれるこの言葉には、人情や優しさがにじむ響きがあります。しかしその「情」が、時に相手の領分を越え、自分自身の不安や焦りからくる“介入”になってしまうこともあるのです。
人間関係において、「ほっとく」「交わさない」「うっちゃる」「そのままにしておく」といった姿勢は、とても高度な対応です。つまり相手の課題に対してすぐに反応せず、あえて余白をつくるという選択です。これは冷たさではなく、信頼や尊重に基づく行動です。
それにもかかわらず、「ほっとけへんのや」という感情に押されると、それがまるで“美徳”のように扱われてしまいます。ここに一つ、線引きをしておきます。
放っておくことの意味と力
放っておくことは「見捨てる」ことではありません。むしろ相手が自分の力で考え、感じ、整理し直すプロセスを見守る姿勢にもつながります。相手の頭の中に関与しすぎないことで、相手が自分のタイミングで戻ってこられる余地が残る。関わらないからこそ、後の対話が練り上がっていくこともあります。
時には、関わらなかったことに罪悪感を抱いたり、「あの時、声をかけていれば…」と後悔の念が浮かぶこともあります。しかしその思いすら、実は“自分の中の納得欲求”にすぎないのです。あくまで相手中心ではなく自分中心になっていることがあります。
相手の衝動をそのまま引き受けずに留める。沈黙の中で考えさせる。そうした「放っておくこと」は、感情ではなく技術となり、力になっていきます。

共依存と決めつけの構図
「ほっとけへん」という感覚が強くなると、相手を“手を差し伸べるべき存在”として固定してしまいます。つまり自分が助ける側であるという役割意識が強まり、「相手はこうに違いない」「自分がなんとかしなきゃ」といった思い込みに結びついていきます。
この構造が進行すると、相手の反応を見ずに行動し、自分の期待通りに動いてくれない相手に対して、怒りや失望が生まれることすらあります。それが「ご利益を仕掛ける」ような構図をつくり、相手との関係性を単純化してしまうのです。
こうした共依存的な関わりの背景には、「今の自分の判断は正しい」という確信の強さがあり、それが関係の自由度を奪っていきます。
境界を尊重するということ
「ほっとけへんのや」は、決して悪意からくる言葉ではありません。むしろ優しさや関心の現れです。しかし無自覚な介入や、自他の境界を曖昧にする行動につながる場合、私たちはその感情に少し距離をとる必要があります。
放っておく。交わさない。見守る。これらは「何もしない」のではなく、「むやみに動かない」という、関係の中での高度な判断です。関わりすぎることなく、しかし無関心でもない。そこに生まれる静かな間合いこそが、人間関係の質を深める鍵になるのです。
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、さまざまな精神的お悩みをお持ちの方のカウンセリングを行っております。下記HPよりお気軽にお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。