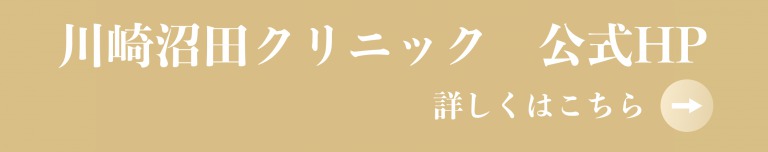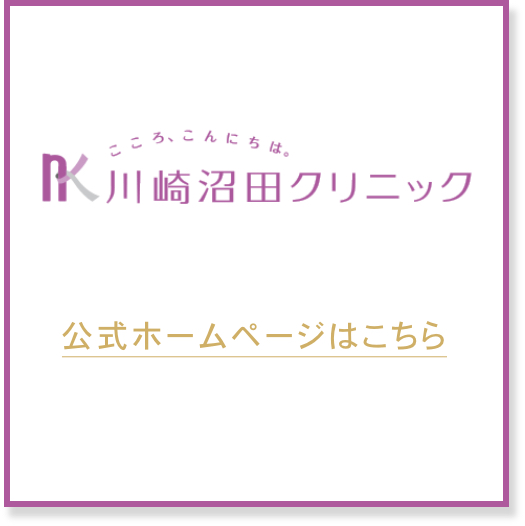21Apr
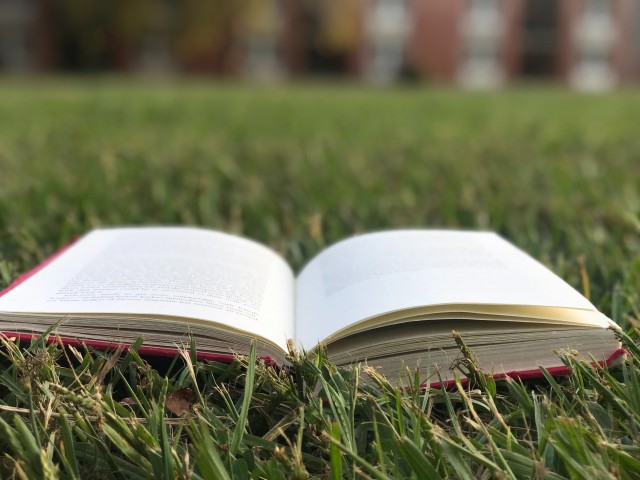
新年度が始まり、緊張感と慌ただしさのなかで4月を乗り越えた頃、ふと気が抜けたような感覚に襲われることがあります。やる気が出ない、職場に行きたくない、身体が重い……そうした状態を人はよく「五月病」と呼びます。ただ、医学的に「五月病」という診断名があるわけではありません。むしろこれは、「こころの反応」としてのひとつの現れなのです。それを踏まえたうえで原因を探りましょう。
五月病とは「病気」ではなく「感情の反応」である?原因を探る
「五月病」という言葉には、「何かに適応できなかった人がなるもの」「弱さの象徴」といった印象がまとわりついていることもあります。しかし実際には、それはごく自然な「感情の反応」です。むしろ感受性が高く、環境の変化に丁寧に反応できる人にこそ起きやすい傾向があります。
新しい人間関係、仕事の覚えごと、生活リズムの変化ー 4月にはたくさんの「新しいこと」が重なります。その緊張状態を何とか維持したまま走り抜けた反動として、5月に入ると身体や心が“揺り戻し”のような反応を起こすことが「五月病」の原因です。これは、壊れかけた機械が「これ以上動くと危険ですよ」と訴えているサインのようなものとも言えます。
五月病の原因として、「過去のこころ」が反応しているということも
五月病のような感覚が起こるとき、実は目の前の出来事だけでなく、「過去の経験」が引き金になっている場合もあります。たとえば、学生時代に新学期になじめなかった記憶や、転勤や異動で孤立した経験など…。そのような“未処理の感情”が、春の環境変化とともに再び心に浮かび上がることが、また五月病の原因となりうるのです。
これは「過去の感情記憶」が、似たような状況に遭遇することで再び活性化される現象です。そのため、本人としては「いま自分は怠けているだけなのかも」と自己否定に向かいやすくなり、結果的に五月病と呼ばれる状態になります。しかし本当は、今の自分ではなく、かつての「うまくいかなかった経験」が原因となり反応しているのです。

五月病の原因を知ったうえで、自分を責めるのではなく反応を見つめること
五月病を「自分の弱さ」として責める必要はまったくありません。むしろ、「今、自分のこころは何に反応しているのだろう?」と、少し立ち止まって原因や背景をじっくり観察してみることが大切です。焦らず、感情の揺らぎに寄り添ってあげること。それが過去の経験との折り合いをつけるきっかけになります。
こころの反応は、無意識にたくさんの情報を汲み取って私たちに教えてくれる“感受性”の表れです。もし、ひとりで抱えるのが難しいと感じたら、ぜひ専門家に相談してみてください。心療内科では、そうした“こころの動き”に耳を傾け、適切な距離感で一緒に整理していくお手伝いをしています。
最後に
川崎市のメンタルクリニック・心療内科・精神科『川崎沼田クリニック』では、五月病のほか、さまざまな精神的お悩みをお持ちの方の診察を行っております。下記HPよりお気軽にお問い合わせください。
https://kawasaki-numata.jp
院長プロフィール
川崎沼田クリニック 院長
日本精神神経学会 専門医
沼田真一

平成12年、秋田大学医学部卒。
同年東北大学医学部精神科に入局後、東北会病院(仙台)嗜癖疾患専門病棟にて併行研修。
平成14年、慶應義塾大学精神科医局に移り、同時に家族機能研究所・さいとうクリニック(東京・港区)で研鑽する。
平成16年、財団法人井之頭病院(東京・三鷹)で、アルコール依存症専門病棟担当医。
平成17年よりはさいとうクリニックで、アルコール依存・摂食障害・DV(虐待)・ひきこもりなど家族問題と精神疾患に従事する傍ら、産業医としての診療や各種のハラスメントなど組織内の人間関係問題に対する相談業務を担う。